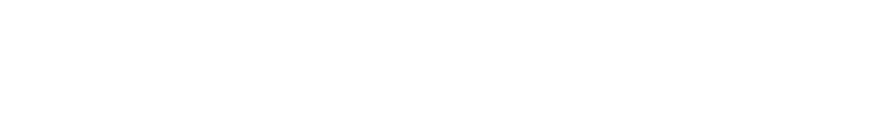エジェクタピンとコアピンの豆知識

細物旋盤加工における歪み抑制のポイント
細物旋盤加工では、ワーク径が細く、加工中の応力や熱の影響を受けやすいため、ほんのわずかな負荷でも歪みが発生しやすい特性があります。特に長尺材や高硬度材では、加工条件や保持方法のわずかな違いが最終寸法に大きく影響します。歪みを抑えた高精度加工を実現するためには、加工前の熱処理工程から、旋盤加工時の突き出し、切削条件、治具設計に至るまで、一連の工程を最適化することが重要です。本記事では、細物旋盤加工における歪みを最小化するための具体的なポイントを解説します。
ポイント①:熱処理時に歪の起きにくい治具を使う
熱処理工程では、温度上昇と冷却の過程で材料内部の応力が変化し、その結果として歪みが生じることがあります。特に細長いワークは熱の影響を受けやすいため、熱処理時に使用する治具設計が重要になります。
歪を抑えるためには、ワークを均一に支持できる治具を使用し、熱が一部に集中しないような保持方法を採用することが効果的です。また、熱処理後の急冷を避け、素材の特性に合わせた適切な冷却方法を選択することで、内部応力の急激な変化を抑えることができます。治具にワークが固定され過ぎると局部応力が発生し、逆に歪みが増える場合もあるため、過拘束にならない支持方法も重要です。
ポイント②:熱処理後の歪とりを行う
細物加工品は、焼入れや調質などの熱処理後に材料内部の応力が解放され、歪みが発生しやすくなります。特に小径部品は断面が小さいため、わずかな応力変化でも曲がりが生じることがあります。このため、熱処理後はまず歪とり作業を行い、真直度を確保することが欠かせません。
歪とりには、専用のハンマーやプレス治具を用いて、曲がり方向を確認しながら少しずつ調整を行います。無理な力を加えると逆方向に過剰に変形する恐れがあるため、素材の反応を見ながら慎重に進めます。
熱処理後の歪を放置したまま旋盤加工に進むと、切削応力によりさらに曲がりが進行する場合があるため、歪とりは細物加工における最初の重要工程といえます。
ポイント③:加工の突き出しに注意する
細物旋盤加工では、ワークの突き出し量が歪み発生の大きな要因となります。突き出しが長くなるほど、切削負荷によるたわみが増加し、加工後にバイト跡の残りや振動痕、真円度の悪化を引き起こす可能性が高まります。そのため、可能な限り突き出し長さを短く設定することが歪み抑制に直結します。
どうしても長尺のまま加工しなければならない場合は、途中で保持位置を変更する段取り変更や、チャック位置を工夫することで負荷を分散させる方法が有効です。また、旋盤の保持力が過大であってもワークに圧痕がつき歪みを引き起こすことがあるため、チャック圧の調整も重要なポイントとなります。
ポイント④:振れ止めを使用する
細物の長尺ワークでは、旋盤加工中の振動を抑制するために振れ止めの活用が欠かせません。振れ止めを使用することで、切削時の外力によるたわみを抑え、刃物との接触位置を安定させることができます。特に外径加工では、バイトの切込みに対してワークがしなることで、削り過ぎや寸法の不一致が起こりやすくなりますが、振れ止めを適切な位置に設置することでこれらの不具合を防ぐことができます。
振れ止めのローラーや接触面の状態も精度に影響するため、使用前の清掃や給油を行い、滑らかにワークを支持できる状態を保つことが重要です。また、振れ止めの位置が加工点から離れ過ぎると効果が薄れるため、加工箇所に近い位置で支持することが理想的です。
ポイント⑤:突き出し量を長くする場合には、片側をセンターで押し支える
ワークの突き出し量が長い場合、たわみを抑制し、加工の安定性を高めるために、ワークの片側をセンターで押し支えるのが効果的です。この方法により、切削抵抗や振動の影響を軽減できます。結果として、工具の折損リスクを最小限に抑えることが可能です。
ポイント⑥:切り込み量を調整する
細物加工における切削負荷は、ほんのわずかな切り込み量の違いで大きく変動します。切り込みが大きすぎるとワークがしなり、歪みや振動が発生しやすくなるため、切り込み量は少量ずつ段階的に設定することが重要です。細物の場合、一度の削り量を減らし、軽切削を繰り返すことで加工中の応力が分散され、仕上がり精度が向上します。
特に小径のシャフトやピン形状の加工では、最終仕上げに向けて切り込みをより浅くし、工具刃先の摩耗も抑えることで、最終寸法を安定化させることができます。
細物旋盤加工では、熱処理から切削、測定までのすべての工程が歪みの発生に関係しており、それぞれのプロセスで最適な管理を行うことが求められます。歪みを抑える取り組みを徹底することで、高精度で安定した加工品質を実現でき、最終製品の信頼性向上につながります。